 › つぶやきホルン › 楽しい活動・旅行編
› つぶやきホルン › 楽しい活動・旅行編2012年10月27日
ドイツ旅行(観光編)マイセン
マイセン 2012年9月17日
そろそろクルーズに飽きてきた頃に、前方の丘の上にマイセンのお城と大聖堂が見えてきました。

お城と大聖堂へはエレベーターがあるという情報を得ていたので、クルーズ船を降りてみんなが行く方(左)とは反対側へ行きましたがほとんど案内がありません。それでも信じて歩いてみるとエレベーターを発見。観光地なんだからもう少し丁寧に案内してよと言いたくなります。
斜めに上るケーブルカーのようなエレベーター(1ユーロ)を降りると、大聖堂と城があるエリアに到着。大聖堂に到着すると、ミサ中ということでしばらく待ってから入場しました。
この大聖堂は非常に立派なもので、礼拝堂が前後2つに分かれており、その他にも小さな礼拝堂がたくさんあるとても変わった造りでした。
アルブレヒト城の方は入場料も結構したし、大したことなさそうだったので外観のみでパス。
でも場外からの眺めはエルベ川を眼下に見て素晴らしいものでした。
「大聖堂」


「アルブレヒト城」

「エルベ川の眺め」

大聖堂のエリアから有名なマイセン磁器の工場へはバスでの移動です。
焼き物好きの私たち夫婦としては、繊細なタッチと1万色以上という色使いの名品の数々に、ただただため息が出るばかりでした。何か買い物をしたかですって??
小さなカップなどは2~3万円で買えるのですが、ほしいなと思うものは小さいものでも10万円以上はします。
目の保養だけさせてもらいました。
「マイセン磁器」

マイセン磁器工場からバスで市街地へ

観光客でにぎわう街の小さなお店をぶらぶらとしていると、ガラス食器の店を発見。なんとマイセンのガラス工房の作品を売っている店です。
マイセンにガラス工場があるなんてガイド本にも載っていません。
でもこれがとても素敵なカットグラスで値段も安いのです。あれもこれもほしいかったのですが持って帰れないので、気に入ったワイングラスなどを少しだけ購入。
磁器工場でつまらない小物を買わなくて本当によかったです。
「マイセングラス」

マイセンからドレスデンへの帰りはDバーンで40分。エルベ川クルーズで眺めた鉄橋を渡って帰りました。
そろそろクルーズに飽きてきた頃に、前方の丘の上にマイセンのお城と大聖堂が見えてきました。

お城と大聖堂へはエレベーターがあるという情報を得ていたので、クルーズ船を降りてみんなが行く方(左)とは反対側へ行きましたがほとんど案内がありません。それでも信じて歩いてみるとエレベーターを発見。観光地なんだからもう少し丁寧に案内してよと言いたくなります。
斜めに上るケーブルカーのようなエレベーター(1ユーロ)を降りると、大聖堂と城があるエリアに到着。大聖堂に到着すると、ミサ中ということでしばらく待ってから入場しました。
この大聖堂は非常に立派なもので、礼拝堂が前後2つに分かれており、その他にも小さな礼拝堂がたくさんあるとても変わった造りでした。
アルブレヒト城の方は入場料も結構したし、大したことなさそうだったので外観のみでパス。
でも場外からの眺めはエルベ川を眼下に見て素晴らしいものでした。
「大聖堂」


「アルブレヒト城」

「エルベ川の眺め」

大聖堂のエリアから有名なマイセン磁器の工場へはバスでの移動です。
焼き物好きの私たち夫婦としては、繊細なタッチと1万色以上という色使いの名品の数々に、ただただため息が出るばかりでした。何か買い物をしたかですって??
小さなカップなどは2~3万円で買えるのですが、ほしいなと思うものは小さいものでも10万円以上はします。
目の保養だけさせてもらいました。
「マイセン磁器」

マイセン磁器工場からバスで市街地へ

観光客でにぎわう街の小さなお店をぶらぶらとしていると、ガラス食器の店を発見。なんとマイセンのガラス工房の作品を売っている店です。
マイセンにガラス工場があるなんてガイド本にも載っていません。
でもこれがとても素敵なカットグラスで値段も安いのです。あれもこれもほしいかったのですが持って帰れないので、気に入ったワイングラスなどを少しだけ購入。
磁器工場でつまらない小物を買わなくて本当によかったです。
「マイセングラス」

マイセンからドレスデンへの帰りはDバーンで40分。エルベ川クルーズで眺めた鉄橋を渡って帰りました。
2012年10月25日
ドイツ旅行(観光編)エルベ川
エルベ川クルーズ 2012年9月17日
ドレスデン旧市街地のホテルから歩いて10分足らずの所にエルベ川クルーズ船の乗り場があります。
この船は蒸気の外輪船で、ドレスデンを起点に上流、下流の様々な都市間を運航しています。

私たちはドレスデンからマイセンまで2時間の船旅を楽しみました。
日本で旅行書を見ていて見つけたもので、息子にチケットを予約してもらいました。
日本からでもホームページで予約できますよ。ただしドイツ語(英語は?)。
9時45分の出発で30分前には余裕を見てホテルを出たのですが、観光ガイド本で見たのとは大違いで、エルベ川沿いにずら~っと船着き場があって色々な船が並んでいます。

マイセン行と表示された客が並んでいる船着き場にしばらくいたのですが、ちょっと不安になって調べてみるとこの船ではありません。
300mほど上流の船着き場だということがわかって大慌て。一生懸命歩いてなんとか間に合いました。
日本の案内表示は世界一丁寧ですが、ドイツはそうはいきません。日本の常識=世界の非常識ですね。
エルベ川クルーズは、有名な城や景観があるわけでもないのですが、ほんとうに素晴らしいドイツらしい景色の連続で、ゆったりした気分を存分に味わうことができました。







マイセンのお城が見えてきました。

ドレスデン旧市街地のホテルから歩いて10分足らずの所にエルベ川クルーズ船の乗り場があります。
この船は蒸気の外輪船で、ドレスデンを起点に上流、下流の様々な都市間を運航しています。

私たちはドレスデンからマイセンまで2時間の船旅を楽しみました。
日本で旅行書を見ていて見つけたもので、息子にチケットを予約してもらいました。
日本からでもホームページで予約できますよ。ただしドイツ語(英語は?)。
9時45分の出発で30分前には余裕を見てホテルを出たのですが、観光ガイド本で見たのとは大違いで、エルベ川沿いにずら~っと船着き場があって色々な船が並んでいます。

マイセン行と表示された客が並んでいる船着き場にしばらくいたのですが、ちょっと不安になって調べてみるとこの船ではありません。
300mほど上流の船着き場だということがわかって大慌て。一生懸命歩いてなんとか間に合いました。
日本の案内表示は世界一丁寧ですが、ドイツはそうはいきません。日本の常識=世界の非常識ですね。
エルベ川クルーズは、有名な城や景観があるわけでもないのですが、ほんとうに素晴らしいドイツらしい景色の連続で、ゆったりした気分を存分に味わうことができました。







マイセンのお城が見えてきました。

2012年10月24日
ドイツ旅行(観光編)ドレスデン
ドレスデン 2012年9月15~18日
ドレスデンは、ザクセン王国の首都として栄えた街で、現在はザクセン州の州都となっています。
エルベ川沿いに広がる旧市街地にはいくつもの塔が立ち並び「これぞドイツの古えのシルエット」と言える景観が見事です。
ドレスデンを訪れたのは、教会音楽やゼン・オーパー(ドレスデン州立歌劇場)でオペラを鑑賞することが第一目的でしたが、この街は、教会などの建築物を見るだけでも十分に見ごたえのある街です。
[移動]
フランクフルト国際空港からドレスデン空港へ飛行機で1時間
ドレスデン空港からはSバーンで旧市街地にあるホテルへ
[ドレスデン旧市街地]

「旧市街地シルエット」

ドイツは第2次世界大戦でほとんどの都市が廃墟と化したわけですが、旧市街地ではそれらの建物がほとんど戦前の姿に復元され、東西統一後その作業はピッチを上げて進んでいます。
「ツヴィンガー宮殿」
ザクセン王が18世紀初期に建てた宮殿
門をくぐると広々とした中庭が広がっています。

この宮殿には様々な絵画館やギャラリーがあるが何といってもお目当ては
GALERIE ALTE MEISTER DRESDEN(ドレスデン古典絵画館)
フェルメール、ルーベンス、ラファエロ、レンブラント、バンダイクなど一枚でも日本に来たら大騒ぎになりそうな有名な(教科書でみたことある)絵画が山のように展示されています。真剣に見ていたら1日でも終わりそうにありません。
中でも有名というかみんなが足を止めているのがラファエロの「システィーナのマドンナ」。
マリアの足元に描かれた2人の天使がかわいらしくてグッズのデザインとして独り歩きしています。

「クロイツ教会」(聖十字教会)
(音楽編)で紹介していますが、Dresdener Kreuz Chor(ドレスデン聖十字架教会合唱団)がとても有名です。

「フラウエン教会」
2005年に復活を遂げた平和の象徴。ドイツで見る教会を始めとした古い様式の建物の外壁に多く見られるのが明るい色と黒い色のモザイク模様。これは戦争で崩れ落ちた古い建物の部材を再建時にできるだけ利用しているからです。


「大聖堂」(カテドラル)

「シュタールホーフの壁画:君主の行列」~ドレスデン城の一部
マイセン磁器25,000枚を使っているそうで16世紀後半のオリジナルだそうです。

「ゼン・オーパー」(ザクセン州立歌劇場~ドレスデン国立歌劇場のこと)

ドレスデンの旧市街地は、3日間滞在したので、この辺りを毎日うろうろとしていました。
もう、これぞドイツという風景に圧倒されっぱなしです。
それにしても、これが実は第二次世界大戦でほとんど破壊され、それを当時のがれきを使いながら復元したというのですから、ドイツ人の執念には脱帽ですね。
ドレスデンは、ザクセン王国の首都として栄えた街で、現在はザクセン州の州都となっています。
エルベ川沿いに広がる旧市街地にはいくつもの塔が立ち並び「これぞドイツの古えのシルエット」と言える景観が見事です。
ドレスデンを訪れたのは、教会音楽やゼン・オーパー(ドレスデン州立歌劇場)でオペラを鑑賞することが第一目的でしたが、この街は、教会などの建築物を見るだけでも十分に見ごたえのある街です。
[移動]
フランクフルト国際空港からドレスデン空港へ飛行機で1時間
ドレスデン空港からはSバーンで旧市街地にあるホテルへ
[ドレスデン旧市街地]

「旧市街地シルエット」

ドイツは第2次世界大戦でほとんどの都市が廃墟と化したわけですが、旧市街地ではそれらの建物がほとんど戦前の姿に復元され、東西統一後その作業はピッチを上げて進んでいます。
「ツヴィンガー宮殿」
ザクセン王が18世紀初期に建てた宮殿
門をくぐると広々とした中庭が広がっています。

この宮殿には様々な絵画館やギャラリーがあるが何といってもお目当ては
GALERIE ALTE MEISTER DRESDEN(ドレスデン古典絵画館)
フェルメール、ルーベンス、ラファエロ、レンブラント、バンダイクなど一枚でも日本に来たら大騒ぎになりそうな有名な(教科書でみたことある)絵画が山のように展示されています。真剣に見ていたら1日でも終わりそうにありません。
中でも有名というかみんなが足を止めているのがラファエロの「システィーナのマドンナ」。
マリアの足元に描かれた2人の天使がかわいらしくてグッズのデザインとして独り歩きしています。

「クロイツ教会」(聖十字教会)
(音楽編)で紹介していますが、Dresdener Kreuz Chor(ドレスデン聖十字架教会合唱団)がとても有名です。

「フラウエン教会」
2005年に復活を遂げた平和の象徴。ドイツで見る教会を始めとした古い様式の建物の外壁に多く見られるのが明るい色と黒い色のモザイク模様。これは戦争で崩れ落ちた古い建物の部材を再建時にできるだけ利用しているからです。


「大聖堂」(カテドラル)

「シュタールホーフの壁画:君主の行列」~ドレスデン城の一部
マイセン磁器25,000枚を使っているそうで16世紀後半のオリジナルだそうです。

「ゼン・オーパー」(ザクセン州立歌劇場~ドレスデン国立歌劇場のこと)

ドレスデンの旧市街地は、3日間滞在したので、この辺りを毎日うろうろとしていました。
もう、これぞドイツという風景に圧倒されっぱなしです。
それにしても、これが実は第二次世界大戦でほとんど破壊され、それを当時のがれきを使いながら復元したというのですから、ドイツ人の執念には脱帽ですね。
2012年10月23日
ドイツ旅行(観光編)フランクフルト
今日からドイツ旅行の観光編です。
今日はほんのさわりで「フランクフルト」を紹介します。
■フランクフルト 2012年9月14日・15日
フランクフルト国際空港はドイツの玄関口。ヨーロッパ屈指のハブ空港として成田空港など比較にならない規模と路線数を誇っています。
今回の旅では、フランクフルトはあくまで旅の玄関口として一泊しただけでしたが、せっかく立ち寄った街ですから、到着したその日のうちにちょっとだけ旧市街地を観光しました。
[移動]
福岡から成田経由でフランクフルトにまで15時間40分
現地時間の16時35分にフランクフルト国際空港に到着


フランクフルト国際空港

タクシーでフランクフルト中央駅前のホテルへ。
フランクフルト中央駅


[フランクフルト旧市街地]
フランクフルト中央駅からSバーン(市内電車)で旧市街地の中心「ハウプトバッヘ駅」へ約10分
ハウプトバッヘ駅からレーマー広場、大聖堂、マイン川方面への散策は「市庁舎」「広場」「教会」というヨーロッパならではの3点セットの街づくりをいきなり堪能させてくれるものでした
レーマー広場

ニコライ教会

大聖堂

食事がてらちょっと見て回っただけでしたが、初めてのヨーロッパだけにいきなり感激してました。
今日はほんのさわりで「フランクフルト」を紹介します。
■フランクフルト 2012年9月14日・15日
フランクフルト国際空港はドイツの玄関口。ヨーロッパ屈指のハブ空港として成田空港など比較にならない規模と路線数を誇っています。
今回の旅では、フランクフルトはあくまで旅の玄関口として一泊しただけでしたが、せっかく立ち寄った街ですから、到着したその日のうちにちょっとだけ旧市街地を観光しました。
[移動]
福岡から成田経由でフランクフルトにまで15時間40分
現地時間の16時35分にフランクフルト国際空港に到着


フランクフルト国際空港

タクシーでフランクフルト中央駅前のホテルへ。
フランクフルト中央駅


[フランクフルト旧市街地]
フランクフルト中央駅からSバーン(市内電車)で旧市街地の中心「ハウプトバッヘ駅」へ約10分
ハウプトバッヘ駅からレーマー広場、大聖堂、マイン川方面への散策は「市庁舎」「広場」「教会」というヨーロッパならではの3点セットの街づくりをいきなり堪能させてくれるものでした
レーマー広場

ニコライ教会

大聖堂

食事がてらちょっと見て回っただけでしたが、初めてのヨーロッパだけにいきなり感激してました。
2012年10月21日
ドイツ旅行(音楽編)その2
音楽編の後半は、2大オーケストラの公演です。
9月20日
ライプツィヒに移動してライプツィヒ・ゲバントハウス管弦楽団の演奏を聴きました。
プログラム
ベートーヴェン : ミサ・ソレムニス(荘厳ミサ曲)~演奏時間約80分間大曲です
指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット
ブロムシュテットさんは、85歳になられたそうで大丈夫かなと思っていましたが、これがとんでもない間違い。
その集中力と言いますか、オーケストラの足並みが乱れそうになったりするとものすごい瞬発力のある棒で「ぐいっと」引っ張っていきます。とにかく恐れ入りました。
この秋にはなんとアクロス福岡にバンベルク交響楽団を率いて来られます。
ソプラノ : SIMONE SCHNEIDER
アルト : GERHILD ROMBERGER
テノール : RICHARD CROET
バス : JOCHEN KUPFER
合唱 中部ドイツ放送合唱団
まずオーケストラが鳴り始めます。
なんとも柔らかい厚みのある、これぞヨーロッパのオーケストラの響きに、ググッと引き込まれます。
そして合唱、日本では聴くことのできない素晴らしい響きです。
もちろんソリストたちの歌声も聴きごたえがありました。
演奏は、キリエ (Kyrie)、グローリア (Gloria)、クレド (Credo)、サンクトゥス (Sanctus)、アニュス・デイ (Agnus Dei)と進み、感動の内に終了しましたが、演奏の余韻が消えても拍手が鳴りません。
いつ拍手をすればいいのかなと迷っていると、指揮者がちょっと振り返り「どうぞ!」というしぐさをしますと割れんばかりの拍手です。
これだけの演奏ですから当然スタンディングオベーションだと思ったらこちらも、誰一人として立ち上がりません。
どうして~?と思っていると、指揮者がカーテンコールで2度目に登場したときにほとんど全員が一斉に立ち上がりました。
なるほど、これがルールなんですかね。
今日はブロムシュテット教の信者??がたくさん聴きに来てるんだなと思いました。
感激してロビーに出てCDショップでしばらく余韻に浸っていると、ちょっとした行列ができ始めました。
何かなと覗いていると、並んでいるおばさんが「ブロムシュテットがサインしてくれるのよ」と教えてくれます。
こりゃ二度とない機会と思い並ぶこと20分、ホールのショップで買ってきたCDにサインをしてもらいました。
ブロムシュテットさんが書いた「日20月9年2012」という漢字が光るサインです。


9月21日
音楽三昧最終日。
念願のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏会です。
プログラム
ハイドン : 交響曲第95番
イェルク・ウィドマン : フルート組曲(2011年作曲)
ベートーヴェン : 交響曲第7番
指揮 : サイモン・ラトル
フルート : エマニュエル・パユ
いよいよ念願かなって、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の本拠地「フィルハーモニー」にやってきました。
「フィルハーモニー」は昨日のゲバントハウスと違って外観はいたって質素な感じで、これっ??と意外な感じがしました。
しかし、中に入ってみるとこれは聞きしに勝るすごさです。
ロビーはとてもゆったりとできていますし、開演前にみんなビールやワインなどを楽しんでいます。
そして、客席ですが、とても複雑な構造になっており、かつ2500席もあるため、慣れないと自分の席を探すだけで疲れてしまいます。
私たちは息子が案内いてくれたので迷わずにすみました。
息子曰く、ホール全体の音響が素晴らしいので、オーケストラの後ろの席でも遜色のない音色で聴けるそうです。
私たちは2カ月ほど前に息子がとても良い席を予約してくれていました。
いよいよ演奏が始まりました。
まずはハイドン。いたってオーソドックスな演奏で、じっくりと落ち着いて素晴らしい音色を楽しむことができました。
チェロのソロも当然ですがめちゃくちゃ上手でしたね。
続いて、おそらくベルリンフィル初演なのでしょう、イェルク・ウィドマンという若い作曲家のフルート組曲です。
現代曲なのですが、とても楽しめる曲でした。
最終曲がバッハの管弦楽組曲第2番の終曲「バディネリ」のパロディー。
「バディネリ」自体もフルートの難曲なのですが、それをパロディーにして、ものすごく難しいパッセージの曲になっています。
ソリストは、現在、世界一と言われるフルート奏者:エマニュエル・パユです。
神業をじっくりと聴かせていただきました。
アクロス福岡の2倍はあると思われるホールの空間をものすごい音量のフルートの音が流れます。
そして終曲では信じられないようなテクニックを披露してくれました。
最後は、ベートーヴェンの交響曲第7番。
サイモンラトルが古典のベトーヴェンをどんな棒を振るのかなと思っていたのですが、私が今まで聴いたベト7でおそらく最も速いテンポだったと思いますし、テンポが揺れる揺れる、これは尋常なベートーヴェンではありません。
終楽章などさしものベルリンフィルも崩壊するのではというスリルを味わうほどの刺激的な演奏でした。
もちろんそこはさすがにベルリンフィルです。
うねるような流れに乗って素晴らしい演奏を聴かせてくれました。
最初の落ち着いたハイドン、パユの名人芸とユーモラスな曲がミックスしたフルート組曲、そして革命的なベト7。
サイモンラトルの世界を十分楽しませていただきました。



これで、今回の音楽三昧のドイツ旅行は終わりです。
数々のすばらしい音楽がたったの2ユーロから50ユーロくらいで楽しめるドイツの人がうらやましい。
何年先になるかわからないけど是非また行ってみたいですね。
息子がこのホールで演奏することがあったらいつ死んでもいいね。
などと、つぶやいてしまいました。
9月20日
ライプツィヒに移動してライプツィヒ・ゲバントハウス管弦楽団の演奏を聴きました。
プログラム
ベートーヴェン : ミサ・ソレムニス(荘厳ミサ曲)~演奏時間約80分間大曲です
指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット
ブロムシュテットさんは、85歳になられたそうで大丈夫かなと思っていましたが、これがとんでもない間違い。
その集中力と言いますか、オーケストラの足並みが乱れそうになったりするとものすごい瞬発力のある棒で「ぐいっと」引っ張っていきます。とにかく恐れ入りました。
この秋にはなんとアクロス福岡にバンベルク交響楽団を率いて来られます。
ソプラノ : SIMONE SCHNEIDER
アルト : GERHILD ROMBERGER
テノール : RICHARD CROET
バス : JOCHEN KUPFER
合唱 中部ドイツ放送合唱団
まずオーケストラが鳴り始めます。
なんとも柔らかい厚みのある、これぞヨーロッパのオーケストラの響きに、ググッと引き込まれます。
そして合唱、日本では聴くことのできない素晴らしい響きです。
もちろんソリストたちの歌声も聴きごたえがありました。
演奏は、キリエ (Kyrie)、グローリア (Gloria)、クレド (Credo)、サンクトゥス (Sanctus)、アニュス・デイ (Agnus Dei)と進み、感動の内に終了しましたが、演奏の余韻が消えても拍手が鳴りません。
いつ拍手をすればいいのかなと迷っていると、指揮者がちょっと振り返り「どうぞ!」というしぐさをしますと割れんばかりの拍手です。
これだけの演奏ですから当然スタンディングオベーションだと思ったらこちらも、誰一人として立ち上がりません。
どうして~?と思っていると、指揮者がカーテンコールで2度目に登場したときにほとんど全員が一斉に立ち上がりました。
なるほど、これがルールなんですかね。
今日はブロムシュテット教の信者??がたくさん聴きに来てるんだなと思いました。
感激してロビーに出てCDショップでしばらく余韻に浸っていると、ちょっとした行列ができ始めました。
何かなと覗いていると、並んでいるおばさんが「ブロムシュテットがサインしてくれるのよ」と教えてくれます。
こりゃ二度とない機会と思い並ぶこと20分、ホールのショップで買ってきたCDにサインをしてもらいました。
ブロムシュテットさんが書いた「日20月9年2012」という漢字が光るサインです。


9月21日
音楽三昧最終日。
念願のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏会です。
プログラム
ハイドン : 交響曲第95番
イェルク・ウィドマン : フルート組曲(2011年作曲)
ベートーヴェン : 交響曲第7番
指揮 : サイモン・ラトル
フルート : エマニュエル・パユ
いよいよ念願かなって、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の本拠地「フィルハーモニー」にやってきました。
「フィルハーモニー」は昨日のゲバントハウスと違って外観はいたって質素な感じで、これっ??と意外な感じがしました。
しかし、中に入ってみるとこれは聞きしに勝るすごさです。
ロビーはとてもゆったりとできていますし、開演前にみんなビールやワインなどを楽しんでいます。
そして、客席ですが、とても複雑な構造になっており、かつ2500席もあるため、慣れないと自分の席を探すだけで疲れてしまいます。
私たちは息子が案内いてくれたので迷わずにすみました。
息子曰く、ホール全体の音響が素晴らしいので、オーケストラの後ろの席でも遜色のない音色で聴けるそうです。
私たちは2カ月ほど前に息子がとても良い席を予約してくれていました。
いよいよ演奏が始まりました。
まずはハイドン。いたってオーソドックスな演奏で、じっくりと落ち着いて素晴らしい音色を楽しむことができました。
チェロのソロも当然ですがめちゃくちゃ上手でしたね。
続いて、おそらくベルリンフィル初演なのでしょう、イェルク・ウィドマンという若い作曲家のフルート組曲です。
現代曲なのですが、とても楽しめる曲でした。
最終曲がバッハの管弦楽組曲第2番の終曲「バディネリ」のパロディー。
「バディネリ」自体もフルートの難曲なのですが、それをパロディーにして、ものすごく難しいパッセージの曲になっています。
ソリストは、現在、世界一と言われるフルート奏者:エマニュエル・パユです。
神業をじっくりと聴かせていただきました。
アクロス福岡の2倍はあると思われるホールの空間をものすごい音量のフルートの音が流れます。
そして終曲では信じられないようなテクニックを披露してくれました。
最後は、ベートーヴェンの交響曲第7番。
サイモンラトルが古典のベトーヴェンをどんな棒を振るのかなと思っていたのですが、私が今まで聴いたベト7でおそらく最も速いテンポだったと思いますし、テンポが揺れる揺れる、これは尋常なベートーヴェンではありません。
終楽章などさしものベルリンフィルも崩壊するのではというスリルを味わうほどの刺激的な演奏でした。
もちろんそこはさすがにベルリンフィルです。
うねるような流れに乗って素晴らしい演奏を聴かせてくれました。
最初の落ち着いたハイドン、パユの名人芸とユーモラスな曲がミックスしたフルート組曲、そして革命的なベト7。
サイモンラトルの世界を十分楽しませていただきました。



これで、今回の音楽三昧のドイツ旅行は終わりです。
数々のすばらしい音楽がたったの2ユーロから50ユーロくらいで楽しめるドイツの人がうらやましい。
何年先になるかわからないけど是非また行ってみたいですね。
息子がこのホールで演奏することがあったらいつ死んでもいいね。
などと、つぶやいてしまいました。
2012年10月19日
ドイツ旅行(音楽編)その1
やっとドイツ旅行の報告の準備が整いました。
しばらくの間、音楽編・観光編・グルメ編・トピックスと順次掲載してまいります。
2012年9月14日から24日にかけてドイツに行ってきました。
一番の目的は、息子が通うハノーファー音楽・演劇大学(Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover)とその街の様子を垣間見ることでしたが、クラシック音楽ファンである私たち夫婦にとっての最大の楽しみは、教会音楽やオペラ、オーケストラ公演でした。
9月14日にフランクフルト国際空港に到着し一夜を過ごした私たちがまず向かったのは、ドレスデンです。
9月15日
17時からDresdener Kreuzchorverper(Kreuz教会の土曜礼拝)と
20時からSemper Oper(ゼンパー・オーパー:ドレスデン州立歌劇場)の「ラ・ボエーム」といういきなりのぜいたくなダブルヘッダーでした。
ドレスデンKreuz教会の土曜礼拝は、ウィーン少年合唱団とも比較されるDresdener Kreuz Chor(ドレスデン聖十字架教会合唱団)のコーラスを聴くことが目的。
この合唱団ができたのは13世紀。9歳から19歳までの少年たちが寄宿生活を送っており、テーオ・アダム、ペーター・シュライアーなど数多くの著名な音楽家を輩出しています。
この日のプログラムは、ブルックナー、ホーミリウス、マックスレーガー、バッハの合唱曲、続いてバッハのオルガン曲(プレリュード)、最後にミサ曲を参列者が加わって全員合唱しました。楽譜が配られていたので私もいい加減なドイツ語で思いっきり声を出してきました。
120~30人の少年合唱は、教会の天上から降り注ぐような、まさに「天使の歌声」のように素晴らしいものでした。
オルガン演奏は、息子曰く、この教会の専属オルガニストは有名な奏者らしいのですが、この日はその人ではなく、きっとアシスタントなのでしょう。ちょっと怪しげなリズム??、ストップの使い方もいまいちで少し残念でした。
約1時間のミサでしたが、いきなり本物の教会音楽に触れることができて、私たちのテンションは上がりっぱなしです。2ユーロで聴けるんですよ。まあ、ミサですから入場料ではなく寄付なのですが、信じられません。

続いて、夜はゼンパー・オーパーの「ラ・ボエーム」へ。
ラ・ボエームはみなさんご存知のとおりプッチーニの有名な歌劇。
あらすじは私のブログで3年ほど前に紹介していますのでご覧ください。
http://horn.yoka-yoka.jp/e221867.html
要するに単純なお涙ちょうだいストーリーですから、良し悪しは歌手やオーケストラの力量と演出が問われます。
この日の公演は、オーケストラも歌手も期待を裏切らない素晴らしいものでした。
特にヨーロッパのオーケストラに共通するまろやかなハーモニーや管楽器の響きは、いきなり「これ!これ!」と私を音楽に引きこんでくれました。
ミミ役のソプラノ歌手の声は特に素晴らしいものでした。
ムゼッタ役がちょっと若すぎたかな??とても素敵なムゼッタらしいいやらしさを出そうとしていたんですがね。
それと、演出。
これが本場イタリアだったらもっともっと「ベタベタ」の終幕だったと思うのですが、ドイツですね。
なんか、さら~っと終わってしまって、「ミミ、もう死んじゃったの?」という感じだったのが少し物足りなさを残しました。


9月16日
この日は、ドレスデン観光だけの予定だったのですが、昨日、Kreuz教会に行ったときに、息子がフラウエン教会のコンサート案内を見つけてくれて、急遽予定を変更しました。
15時から、フラウエン教会において、こちらもミサではあるのですが、昨日のKreuz教会の礼拝よりは、コンサート的に構成されており、入場料も確か12ユーロほどだったと思います。その証拠に、昨日の演奏は最初から最後まで一切拍手はありません。しかし、この日は、プログラムの最後の演奏が終わったところで大きな拍手に包まれました。
プログラム
バッハ Overture g-Moll BWV1070(弦楽合奏)
プレリュードとフーガ e-Moll BWV548(オルガン)
説教
メンデルスゾーン
Wer nur den lieben Gott läßt walten(ただ愛する神の力に委ねる者は)
モーツァルト Laudate Dominum(主を褒め称えよ)
オーケストラも合唱もオルガンもすべてこの教会の専属なのですが、やはりとてもレベルが高いですね。
メンデルスゾーンもモーツァルトも最初はどんな曲かなと思っていたのですが、これまでに何度も聞いたことのあるなじみ深い曲でした。

息子が、ドイツに来るときは土曜日、日曜日を外してはいけないと言ってくれた理由が良くわかりました。
ドレスデン聖十字架教会合唱団は特別としても、大きな教会はほとんどが専属の合唱団やオルガニスト、場合によってはオーケストラまで抱えているようですし、大きな教会からやや小さめの教会まで、ほんとうにあちらこちらの教会でミサを兼ねたコンサートが開かれています。
ドレスデンKreuz教会のように定期的に毎週やっているものは事前にホームページ等で調べることができますし、分からなくても金曜日に街に入って一番大きな教会を尋ねれば、そこに他の教会の情報なども貼ってある場合があるようで、なんらかの演奏は間違いなく聴けそうです。
これで、前半の音楽の旅は終了です。
旅の中盤は演奏会はありませんでした。
ちょこちょこと音楽に出会うことはありましたが。
だって、あちらこちらの教会でミサをやってましたし、
大道で色々なアンサンブルをやっているのです。
しかも結構うまい。
きっと音大生や楽団員のアルバイトかもしれません。
少なくともそんじょそこらの音大出よりは上手かもしれません。
9月18日
息子が通うハノーファー音楽・演劇大学を少しだけ見学しました。
思った以上にこじんまりした大学ですが、ここに世界中から優秀な先生を訪ねて学生が集まっているのだなと思うと不思議な感じがします。
息子もハノーファー音楽・演劇大学に入学してはや3年半になりますが、これまでアイナーステーン・ネックレベルク教授に師事し、この10月からはマルクス・ベッカー教授のもとで室内楽を中心とした勉強を始めます。
ベッカー教授はまだ40歳台、ベルリンフィルのトップメンバーとCDを何枚も出しています。
なかなか将来の展望は開けませんが、素晴らしい環境で勉強していることだけは確かなようです。

9月19日
ハノーファーから1時間半ほどのブレーメンに行きました。
もちろん観光が目的ですが、この街に息子の行きつけの楽譜屋さんがあるというのでちょっと立ち寄ってみました。
確かに膨大な楽譜がそろっています。
日本では、ササヤか神戸楽譜が有名ですが、おそらく比較にならないくらいすごいし、楽譜の値段が半額程度ではないかと思います。
残念ながら探したい曲を考えてこなかったので購入はしませんでしたが、今後は息子に頼めば大概の曲が安く手に入ることが分かりました。
もちろん急ぐ楽譜は日本で購入しますが、1年先でもいいようなものはドイツで購入しましょう。
これは収穫です。
次回は後半の2大オーケストラ公演です。
しばらくの間、音楽編・観光編・グルメ編・トピックスと順次掲載してまいります。
2012年9月14日から24日にかけてドイツに行ってきました。
一番の目的は、息子が通うハノーファー音楽・演劇大学(Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover)とその街の様子を垣間見ることでしたが、クラシック音楽ファンである私たち夫婦にとっての最大の楽しみは、教会音楽やオペラ、オーケストラ公演でした。
9月14日にフランクフルト国際空港に到着し一夜を過ごした私たちがまず向かったのは、ドレスデンです。
9月15日
17時からDresdener Kreuzchorverper(Kreuz教会の土曜礼拝)と
20時からSemper Oper(ゼンパー・オーパー:ドレスデン州立歌劇場)の「ラ・ボエーム」といういきなりのぜいたくなダブルヘッダーでした。
ドレスデンKreuz教会の土曜礼拝は、ウィーン少年合唱団とも比較されるDresdener Kreuz Chor(ドレスデン聖十字架教会合唱団)のコーラスを聴くことが目的。
この合唱団ができたのは13世紀。9歳から19歳までの少年たちが寄宿生活を送っており、テーオ・アダム、ペーター・シュライアーなど数多くの著名な音楽家を輩出しています。
この日のプログラムは、ブルックナー、ホーミリウス、マックスレーガー、バッハの合唱曲、続いてバッハのオルガン曲(プレリュード)、最後にミサ曲を参列者が加わって全員合唱しました。楽譜が配られていたので私もいい加減なドイツ語で思いっきり声を出してきました。
120~30人の少年合唱は、教会の天上から降り注ぐような、まさに「天使の歌声」のように素晴らしいものでした。
オルガン演奏は、息子曰く、この教会の専属オルガニストは有名な奏者らしいのですが、この日はその人ではなく、きっとアシスタントなのでしょう。ちょっと怪しげなリズム??、ストップの使い方もいまいちで少し残念でした。
約1時間のミサでしたが、いきなり本物の教会音楽に触れることができて、私たちのテンションは上がりっぱなしです。2ユーロで聴けるんですよ。まあ、ミサですから入場料ではなく寄付なのですが、信じられません。

続いて、夜はゼンパー・オーパーの「ラ・ボエーム」へ。
ラ・ボエームはみなさんご存知のとおりプッチーニの有名な歌劇。
あらすじは私のブログで3年ほど前に紹介していますのでご覧ください。
http://horn.yoka-yoka.jp/e221867.html
要するに単純なお涙ちょうだいストーリーですから、良し悪しは歌手やオーケストラの力量と演出が問われます。
この日の公演は、オーケストラも歌手も期待を裏切らない素晴らしいものでした。
特にヨーロッパのオーケストラに共通するまろやかなハーモニーや管楽器の響きは、いきなり「これ!これ!」と私を音楽に引きこんでくれました。
ミミ役のソプラノ歌手の声は特に素晴らしいものでした。
ムゼッタ役がちょっと若すぎたかな??とても素敵なムゼッタらしいいやらしさを出そうとしていたんですがね。
それと、演出。
これが本場イタリアだったらもっともっと「ベタベタ」の終幕だったと思うのですが、ドイツですね。
なんか、さら~っと終わってしまって、「ミミ、もう死んじゃったの?」という感じだったのが少し物足りなさを残しました。


9月16日
この日は、ドレスデン観光だけの予定だったのですが、昨日、Kreuz教会に行ったときに、息子がフラウエン教会のコンサート案内を見つけてくれて、急遽予定を変更しました。
15時から、フラウエン教会において、こちらもミサではあるのですが、昨日のKreuz教会の礼拝よりは、コンサート的に構成されており、入場料も確か12ユーロほどだったと思います。その証拠に、昨日の演奏は最初から最後まで一切拍手はありません。しかし、この日は、プログラムの最後の演奏が終わったところで大きな拍手に包まれました。
プログラム
バッハ Overture g-Moll BWV1070(弦楽合奏)
プレリュードとフーガ e-Moll BWV548(オルガン)
説教
メンデルスゾーン
Wer nur den lieben Gott läßt walten(ただ愛する神の力に委ねる者は)
モーツァルト Laudate Dominum(主を褒め称えよ)
オーケストラも合唱もオルガンもすべてこの教会の専属なのですが、やはりとてもレベルが高いですね。
メンデルスゾーンもモーツァルトも最初はどんな曲かなと思っていたのですが、これまでに何度も聞いたことのあるなじみ深い曲でした。

息子が、ドイツに来るときは土曜日、日曜日を外してはいけないと言ってくれた理由が良くわかりました。
ドレスデン聖十字架教会合唱団は特別としても、大きな教会はほとんどが専属の合唱団やオルガニスト、場合によってはオーケストラまで抱えているようですし、大きな教会からやや小さめの教会まで、ほんとうにあちらこちらの教会でミサを兼ねたコンサートが開かれています。
ドレスデンKreuz教会のように定期的に毎週やっているものは事前にホームページ等で調べることができますし、分からなくても金曜日に街に入って一番大きな教会を尋ねれば、そこに他の教会の情報なども貼ってある場合があるようで、なんらかの演奏は間違いなく聴けそうです。
これで、前半の音楽の旅は終了です。
旅の中盤は演奏会はありませんでした。
ちょこちょこと音楽に出会うことはありましたが。
だって、あちらこちらの教会でミサをやってましたし、
大道で色々なアンサンブルをやっているのです。
しかも結構うまい。
きっと音大生や楽団員のアルバイトかもしれません。
少なくともそんじょそこらの音大出よりは上手かもしれません。
9月18日
息子が通うハノーファー音楽・演劇大学を少しだけ見学しました。
思った以上にこじんまりした大学ですが、ここに世界中から優秀な先生を訪ねて学生が集まっているのだなと思うと不思議な感じがします。
息子もハノーファー音楽・演劇大学に入学してはや3年半になりますが、これまでアイナーステーン・ネックレベルク教授に師事し、この10月からはマルクス・ベッカー教授のもとで室内楽を中心とした勉強を始めます。
ベッカー教授はまだ40歳台、ベルリンフィルのトップメンバーとCDを何枚も出しています。
なかなか将来の展望は開けませんが、素晴らしい環境で勉強していることだけは確かなようです。

9月19日
ハノーファーから1時間半ほどのブレーメンに行きました。
もちろん観光が目的ですが、この街に息子の行きつけの楽譜屋さんがあるというのでちょっと立ち寄ってみました。
確かに膨大な楽譜がそろっています。
日本では、ササヤか神戸楽譜が有名ですが、おそらく比較にならないくらいすごいし、楽譜の値段が半額程度ではないかと思います。
残念ながら探したい曲を考えてこなかったので購入はしませんでしたが、今後は息子に頼めば大概の曲が安く手に入ることが分かりました。
もちろん急ぐ楽譜は日本で購入しますが、1年先でもいいようなものはドイツで購入しましょう。
これは収穫です。
次回は後半の2大オーケストラ公演です。
2011年08月31日
夏の思い出Part2
8月5日に無事息子の演奏会が終わりほっとしたところで・・・・
せっかくの京都ですからやはり観光ですね。
でも、昨年は、貴船、一昨年は嵐山と・・・
一通り京都観光は済みですから・・・ちょと考えてしまいました。
それもめっちゃ暑い夏の盛りの京都
だれも観光などしませんよね???
それでも、ふっと思ったのは、
大原って、行ったのいつだったかな???
ちょっと山手だから、
もしかしたら少しは涼しいかも、
という訳で、
何十年ぶりかわからないけど大原へ・・・
寂光院と三千院という
いたっておきまりのコースでしたが
人も少なく、
オフシーズンの大原はなかなか正解でした。
紅葉の秋になると
もみじより人のほうが多かったりして??




せっかくの京都ですからやはり観光ですね。
でも、昨年は、貴船、一昨年は嵐山と・・・
一通り京都観光は済みですから・・・ちょと考えてしまいました。
それもめっちゃ暑い夏の盛りの京都
だれも観光などしませんよね???
それでも、ふっと思ったのは、
大原って、行ったのいつだったかな???
ちょっと山手だから、
もしかしたら少しは涼しいかも、
という訳で、
何十年ぶりかわからないけど大原へ・・・
寂光院と三千院という
いたっておきまりのコースでしたが
人も少なく、
オフシーズンの大原はなかなか正解でした。
紅葉の秋になると
もみじより人のほうが多かったりして??
2010年12月27日
メキシコ旅行6日目
メキシコ6日目 8月27日は、実質的なメキシコ観光最終日です。
私たちは、メキシコの有名なお酒、テキーラの発祥の地というテキーラ村に向かいました。
テキーラ村はグアダラハラから北西に約50km。村に近づくと、辺りはテキーラの材料である「アガベ」(竜舌蘭の一種)の畑が広がっています。




テキーラ村近くの風景・テキーラ村の街並み、最初にできた教会
テキーラは、マルガリータなどカクテルで飲まれるようになってから世界中で飲まれるようになったそうで、今では材料のアガベが不足するくらいだそうです。
テキーラが有名になって、テキーラ村以外の地域でも生産されるようになったのですが、これらはテキーラとは呼ばないんですって。シャンパンがシャンパーニュ地方のお酒であるのと同じなのでしょう。
私たちは、クエルボという最も有名なテキーラ工場を見学しました。
工場に入ると辺り一面に甘い香りが漂っています。これこそアガベの絞り汁の臭いです。
絞り立ては3%ほどのアルコール分ですが、これを数回蒸留すると40~50%の強いお酒になるそうです。



テキーラ工場の内部・原料のアガベ・クエルボのシンボル「カラス」(クエルボ=創業者の名前がカラスの意味)
できたてのテキーラは相当強いお酒ですが、とっても甘みがあってどちらかというと美味しいブランデーに近いように思いました。でも瓶詰めしたものをいただくとそれほどでもなかったのでおみやげとして買うのはやめました。持って帰るのに重くて大変なのもありますが、アメリカ経由で帰国すると、アメリカでは液体が全部没収されるそうで持って帰れないのです。
その分、現地にいる内にしっかりと楽しむことにして、テキーラ村での昼食で、最後のメキシコ料理とマルガリータをたっぷりといただきました。



様々なメーカーのテキーラ・マルガリータ・バーカウンター
これで私たちのメキシコ旅行は終了です。
28日は早朝にホテルを出発してグアダラハラ空港からダラス空港へ、そして成田から福岡へとただただ乗り継いで帰るだけです。
でもこの帰りの旅がえらく大変でした。
グアダラハラ空港では、とても厳しい手荷物検査を経て、待合室から飛行機に乗り込むときに「な・な・なんと!!」またまた手荷物検査?? 中身を全部かき混ぜられるんですよ。なんでも麻薬の密輸がターゲットだそうです。こんなことやってるものだから搭乗が相当遅れました。
やっとの思いで搭乗すると、嫁さんの座席のリクライニングが壊れて少し倒れたまま。
これを搭乗員に指摘すると、これからが大変。
修理できるまでパイロットが飛べないと言っている、ということで応急修理の開始。
結局これでまた1時間くらいのロスタイム。
結局2時間近くも遅れて離陸したものですから、ダラスの乗り継ぎが大ピンチに。
ダラスでは、ぶっちょの空港係員のあばさんがあんまり私をせかすものだから、日本語で「あほか~~!!」と叫びながら何とか搭乗できました。
ということで、なんとか無事終了できることになったメキシコ旅行でした。
私たちは、メキシコの有名なお酒、テキーラの発祥の地というテキーラ村に向かいました。
テキーラ村はグアダラハラから北西に約50km。村に近づくと、辺りはテキーラの材料である「アガベ」(竜舌蘭の一種)の畑が広がっています。




テキーラ村近くの風景・テキーラ村の街並み、最初にできた教会
テキーラは、マルガリータなどカクテルで飲まれるようになってから世界中で飲まれるようになったそうで、今では材料のアガベが不足するくらいだそうです。
テキーラが有名になって、テキーラ村以外の地域でも生産されるようになったのですが、これらはテキーラとは呼ばないんですって。シャンパンがシャンパーニュ地方のお酒であるのと同じなのでしょう。
私たちは、クエルボという最も有名なテキーラ工場を見学しました。
工場に入ると辺り一面に甘い香りが漂っています。これこそアガベの絞り汁の臭いです。
絞り立ては3%ほどのアルコール分ですが、これを数回蒸留すると40~50%の強いお酒になるそうです。



テキーラ工場の内部・原料のアガベ・クエルボのシンボル「カラス」(クエルボ=創業者の名前がカラスの意味)
できたてのテキーラは相当強いお酒ですが、とっても甘みがあってどちらかというと美味しいブランデーに近いように思いました。でも瓶詰めしたものをいただくとそれほどでもなかったのでおみやげとして買うのはやめました。持って帰るのに重くて大変なのもありますが、アメリカ経由で帰国すると、アメリカでは液体が全部没収されるそうで持って帰れないのです。
その分、現地にいる内にしっかりと楽しむことにして、テキーラ村での昼食で、最後のメキシコ料理とマルガリータをたっぷりといただきました。



様々なメーカーのテキーラ・マルガリータ・バーカウンター
これで私たちのメキシコ旅行は終了です。
28日は早朝にホテルを出発してグアダラハラ空港からダラス空港へ、そして成田から福岡へとただただ乗り継いで帰るだけです。
でもこの帰りの旅がえらく大変でした。
グアダラハラ空港では、とても厳しい手荷物検査を経て、待合室から飛行機に乗り込むときに「な・な・なんと!!」またまた手荷物検査?? 中身を全部かき混ぜられるんですよ。なんでも麻薬の密輸がターゲットだそうです。こんなことやってるものだから搭乗が相当遅れました。
やっとの思いで搭乗すると、嫁さんの座席のリクライニングが壊れて少し倒れたまま。
これを搭乗員に指摘すると、これからが大変。
修理できるまでパイロットが飛べないと言っている、ということで応急修理の開始。
結局これでまた1時間くらいのロスタイム。
結局2時間近くも遅れて離陸したものですから、ダラスの乗り継ぎが大ピンチに。
ダラスでは、ぶっちょの空港係員のあばさんがあんまり私をせかすものだから、日本語で「あほか~~!!」と叫びながら何とか搭乗できました。
ということで、なんとか無事終了できることになったメキシコ旅行でした。
タグ :メキシコ
2010年12月26日
メキシコ旅行5日目
旅行5日目の8月26日は、午前中は世界文化資産の「オスピシオ・カバーニャス」とその周辺の界隈を、マルコという息子の知人のピアニストに案内してもらいました。また昼からは親善相撲公演、その後郊外のトラケパケ夕村にある民芸品などの専門店街でおみやげ品のショッピング、夕方から前日に息子の演奏会があったデゴジャード劇場での親善バレエ公演等の鑑賞、そして夜は京都市が主催する答礼のパーティーと大忙しの一日でした。
「オスピシオ・カバーニャス」は1810年にカバーニャス伯爵によって建てられた病院施設を持つ孤児院で、オロスコが描いた「スペインのメキシコ侵略」と称される巨大な壁画や天井画によって「世界文化遺産」に登録されています。内部は礼拝堂になっており、壮大な外観、壁画群、そしてとても洒落たパティオ(中庭)などとても魅力的な場所でした。





私たちはそこから、下町へと入って行きました。ここからはビデオ撮影などはやめた方が良いというマルコの忠告もあり、撮影は控えました。もともとグアダラハラはメキシコで最も治安の良いと言われる都市ですから心配はいりませんでしたが。



午後の親善相撲公演は京都市の小・中学校の先生たちによるアマチュア相撲の披露です。
アマチュアとは言え、初めて見る相撲の迫力にメキシコの子どもたちは大喜びでした。




その後タクシーで向かったトラケパケ夕村では、とても楽しいおみやげ物のショッピングです。トラケパケ夕村はもともととても古い村だそうですが、その中心部に今はおみやげ物屋が200軒ほど軒を並べています。銀製品や革製品、おみやげ物がなんでも揃いそうです。とても気に入った店では、カロ(高い)の連発で一所懸命値切り交渉です。
最後は、店の主人から「あなたはメキシコ人のようだ」と言われてしまいましたよ。




答礼パーティーは、ホテルメンドーサの屋上で行われました。
グアダラハラ市からは、今回の親善講演の貢献者たちに記念品としてとても鮮やかな織物が贈られ、息子もいただきました。
「オスピシオ・カバーニャス」は1810年にカバーニャス伯爵によって建てられた病院施設を持つ孤児院で、オロスコが描いた「スペインのメキシコ侵略」と称される巨大な壁画や天井画によって「世界文化遺産」に登録されています。内部は礼拝堂になっており、壮大な外観、壁画群、そしてとても洒落たパティオ(中庭)などとても魅力的な場所でした。





私たちはそこから、下町へと入って行きました。ここからはビデオ撮影などはやめた方が良いというマルコの忠告もあり、撮影は控えました。もともとグアダラハラはメキシコで最も治安の良いと言われる都市ですから心配はいりませんでしたが。



午後の親善相撲公演は京都市の小・中学校の先生たちによるアマチュア相撲の披露です。
アマチュアとは言え、初めて見る相撲の迫力にメキシコの子どもたちは大喜びでした。




その後タクシーで向かったトラケパケ夕村では、とても楽しいおみやげ物のショッピングです。トラケパケ夕村はもともととても古い村だそうですが、その中心部に今はおみやげ物屋が200軒ほど軒を並べています。銀製品や革製品、おみやげ物がなんでも揃いそうです。とても気に入った店では、カロ(高い)の連発で一所懸命値切り交渉です。
最後は、店の主人から「あなたはメキシコ人のようだ」と言われてしまいましたよ。




答礼パーティーは、ホテルメンドーサの屋上で行われました。
グアダラハラ市からは、今回の親善講演の貢献者たちに記念品としてとても鮮やかな織物が贈られ、息子もいただきました。
タグ :メキシコ
2010年10月26日
メキシコ旅行ー日本庭園
8月25日の朝、私たちはグアダラハラ市の郊外にあるコロムス公園の日本庭園を見学に行きました。

この日本庭園は、京都市とグアダラハラ市の姉妹都市締結10周年を記念して京都市から贈られたものです。
実は私も20年ほど前に、福岡市からニュージーランドのオークランド市に派遣されて、日本庭園を造ったことがあります。こちらはオークランド動物園の中でわずかに250㎡程度の小さなものです。それでも外国で日本庭園を造ることの難しさを十分味わいました。
しかし、コロムス公園の日本庭園はさすがに京都市からの贈り物だけあって桁違いに立派です。数千㎡はあります。
なんでも、岡崎文彬京都大学名誉教授のアドバイスで京都を代表する醍醐寺三宝院の池泉回遊式庭園をモデルとすべきとのアドバイスがあったそうです。
因みにこの岡崎文彬先生は、私が京都大学で造園学を学ぶきっかけとなった方で、この先生に教えを請うために京都大学に入学したのですが、一度だけお話を聞いただけで定年退官されてしまいました。私の一生の不覚なのです。
それは良いとして、作庭にあたってグアダラハラ市の青年造園家が作庭技術を学ぶために6ヶ月間京都市で研修を受け、さらに有名な庭師の佐野藤右衛門氏率いる京都府造園協同組合が造園工事を引き受けて1994年に完成したそうです。
佐野藤右衛門氏は、今の方は確か16代目だと思うのですが、京都の桜守として全国に名を馳せている方です。特に15代が植えた円山公園の祇園しだれは有名ですね。
確かに細部に目をやれば、やや大作りで繊細さには欠けるのですが、外国にある日本庭園としては秀逸だと思います。


さらに感心したのは、良く手入れされていることです。
庭園は、造ったときが完成ではなく、樹木の成長とともに長年手入れすることで魅力が増してきます。
日本庭園をずっと手入れできるメキシコの人をまず育てたことがこの素晴らしい庭園を持続させているのだと感心させられました。
園内でなんとハチドリの撮影に成功


この日本庭園は、京都市とグアダラハラ市の姉妹都市締結10周年を記念して京都市から贈られたものです。
実は私も20年ほど前に、福岡市からニュージーランドのオークランド市に派遣されて、日本庭園を造ったことがあります。こちらはオークランド動物園の中でわずかに250㎡程度の小さなものです。それでも外国で日本庭園を造ることの難しさを十分味わいました。
しかし、コロムス公園の日本庭園はさすがに京都市からの贈り物だけあって桁違いに立派です。数千㎡はあります。
なんでも、岡崎文彬京都大学名誉教授のアドバイスで京都を代表する醍醐寺三宝院の池泉回遊式庭園をモデルとすべきとのアドバイスがあったそうです。
因みにこの岡崎文彬先生は、私が京都大学で造園学を学ぶきっかけとなった方で、この先生に教えを請うために京都大学に入学したのですが、一度だけお話を聞いただけで定年退官されてしまいました。私の一生の不覚なのです。
それは良いとして、作庭にあたってグアダラハラ市の青年造園家が作庭技術を学ぶために6ヶ月間京都市で研修を受け、さらに有名な庭師の佐野藤右衛門氏率いる京都府造園協同組合が造園工事を引き受けて1994年に完成したそうです。
佐野藤右衛門氏は、今の方は確か16代目だと思うのですが、京都の桜守として全国に名を馳せている方です。特に15代が植えた円山公園の祇園しだれは有名ですね。
確かに細部に目をやれば、やや大作りで繊細さには欠けるのですが、外国にある日本庭園としては秀逸だと思います。


さらに感心したのは、良く手入れされていることです。
庭園は、造ったときが完成ではなく、樹木の成長とともに長年手入れすることで魅力が増してきます。
日本庭園をずっと手入れできるメキシコの人をまず育てたことがこの素晴らしい庭園を持続させているのだと感心させられました。
園内でなんとハチドリの撮影に成功

2010年10月19日
メキシコ旅行ーグアダラハラ
私たちはメキシコシティに2泊したあと、最終目的地のグアダラハラに移動しました。
グアダラハラは、メキシコシティから北北西に約500km、飛行機で1.5時間くらいの所にあります。
飛行機を降りたとき、メキシコシティと比べるとほんの少し暑さを感じました。
それもそのはず、メキシコシティの標高が約2200mであるのに対して、グアダラハラは標高約1500m。でもやっぱり涼しいですね。

グアダラハラは、ハリスコ州の州都でメキシコシティに次ぐメキシコ第2の都市です。資料によると人口約165万人、都市圏人口は約370万人と書かれています。でも現地ガイドによると最近5年くらいで人口は爆発的に増加しており、800万人になっているとうことでした。
メキシコで驚くのは、メキシコシティもグアダラハラも、とにかく街中に人があふれていると言うことです、昼の日中から街角のいたるところでたくさんの男達がたわむれて話し込んでいます。休日でもないのに広場はたくさんの人でにぎわっています。それに若者が多いのもメキシコの特徴です。なんでも20歳以下の人口が70%だそうです。仕事がないので人がぶらぶらしているのも事実ですが、超高齢社会を目前にした日本からみれば、メキシコはまさにこれから日が昇ろうとしている感じでした。



平日と言うのに街は人だらけです。



たまたま出くわしたパレード。ロデオの原型・チャロも見ることができました。
グアダラハラは1530年にスペイン人が入植して拓かれたスペインの面影を色濃く残す古都で、メキシコ人からはその美しさから「西部の真珠」と呼ばれているそうです。
確かにその名のとおりとてもきれいな街です。
世界遺産に指定されている「オスピシオ・カバーニャス(昔の孤児院)」をはじめ、「ソカロ(中央広場)」を取り囲むように建っている「カテドラル(大聖堂)」や「デゴジャード劇場(築150年の素晴らしいホールで、ここで息子が今回演奏しました)」「ハリスコ州庁舎」などまさに古いヨーロッパの街並みそのものです。


私たちが泊まった「ホテル デ メンドーサ」も実は16世紀頃から続くサントドミンゴ修道院跡で、とても素敵な教会が隣接していました。今回の旅行ではいくつかの古い教会を見ることができましたが、この教会の清楚で落ち着いた感じが一番気に入りました。



確かに東京の喧噪と京都の落ち着きを対比すると、メキシコシティとグアダラハラの関係に近いような気がします。日本の古都である京都市と30年前に姉妹都市になったのもうなずけますね。
また、街の中は、道路などもよく清掃されています。治安もメキシコの中では最も良いそうですよ。
そのほか、グアダラハラは、結婚式や祝宴の場で陽気な演奏と歌を披露するメキシコ音楽「マリアッチ」の発祥の地、また中心部から50kmにあるテキーラ村は世界的に有名なメキシコのお酒「テキーラ」の生産地テキーラ村、そして美人の産地?としても有名です。
なんと私たちが滞在中に今年のミス・ユニバースがグアダラハラから誕生したというニュースが舞い込みました。確かにチャーミングな美人にたくさん出会いました。
なんでも、グアダラハラはフランス軍が侵攻してきた際に、それまでの現地人とスペイン人の混血に、フランス人の血が混ざったことからすばらしい美人が誕生するようになったのだそうです。
 美人のたまご
美人のたまご
メキシコに行くなら、絶対にお勧めの場所ですね。
グアダラハラは、メキシコシティから北北西に約500km、飛行機で1.5時間くらいの所にあります。
飛行機を降りたとき、メキシコシティと比べるとほんの少し暑さを感じました。
それもそのはず、メキシコシティの標高が約2200mであるのに対して、グアダラハラは標高約1500m。でもやっぱり涼しいですね。

グアダラハラは、ハリスコ州の州都でメキシコシティに次ぐメキシコ第2の都市です。資料によると人口約165万人、都市圏人口は約370万人と書かれています。でも現地ガイドによると最近5年くらいで人口は爆発的に増加しており、800万人になっているとうことでした。
メキシコで驚くのは、メキシコシティもグアダラハラも、とにかく街中に人があふれていると言うことです、昼の日中から街角のいたるところでたくさんの男達がたわむれて話し込んでいます。休日でもないのに広場はたくさんの人でにぎわっています。それに若者が多いのもメキシコの特徴です。なんでも20歳以下の人口が70%だそうです。仕事がないので人がぶらぶらしているのも事実ですが、超高齢社会を目前にした日本からみれば、メキシコはまさにこれから日が昇ろうとしている感じでした。
平日と言うのに街は人だらけです。
たまたま出くわしたパレード。ロデオの原型・チャロも見ることができました。
グアダラハラは1530年にスペイン人が入植して拓かれたスペインの面影を色濃く残す古都で、メキシコ人からはその美しさから「西部の真珠」と呼ばれているそうです。
確かにその名のとおりとてもきれいな街です。
世界遺産に指定されている「オスピシオ・カバーニャス(昔の孤児院)」をはじめ、「ソカロ(中央広場)」を取り囲むように建っている「カテドラル(大聖堂)」や「デゴジャード劇場(築150年の素晴らしいホールで、ここで息子が今回演奏しました)」「ハリスコ州庁舎」などまさに古いヨーロッパの街並みそのものです。


私たちが泊まった「ホテル デ メンドーサ」も実は16世紀頃から続くサントドミンゴ修道院跡で、とても素敵な教会が隣接していました。今回の旅行ではいくつかの古い教会を見ることができましたが、この教会の清楚で落ち着いた感じが一番気に入りました。



確かに東京の喧噪と京都の落ち着きを対比すると、メキシコシティとグアダラハラの関係に近いような気がします。日本の古都である京都市と30年前に姉妹都市になったのもうなずけますね。
また、街の中は、道路などもよく清掃されています。治安もメキシコの中では最も良いそうですよ。
そのほか、グアダラハラは、結婚式や祝宴の場で陽気な演奏と歌を披露するメキシコ音楽「マリアッチ」の発祥の地、また中心部から50kmにあるテキーラ村は世界的に有名なメキシコのお酒「テキーラ」の生産地テキーラ村、そして美人の産地?としても有名です。
なんと私たちが滞在中に今年のミス・ユニバースがグアダラハラから誕生したというニュースが舞い込みました。確かにチャーミングな美人にたくさん出会いました。
なんでも、グアダラハラはフランス軍が侵攻してきた際に、それまでの現地人とスペイン人の混血に、フランス人の血が混ざったことからすばらしい美人が誕生するようになったのだそうです。
メキシコに行くなら、絶対にお勧めの場所ですね。
2010年10月15日
メキシコ旅行ーメキシコ国立自治大学
8月24日は、午前中はメキシコシティ郊外の「メキシコ国立自治大学」を見学しました。
アメリカ大陸で2番目に古い大学だそうです。
どれくらいの広さかはわかりませんがとにかく広大なキャンパスに、メキシコオリンピックの会場にもなった陸上競技場などがあります。
この大学は、歴史的な多くの壁画が建物に描かれており、これらの壁画があることによって「世界文化遺産」に登録されています。
メキシコの壁画運動は、1910年代から40年頃にかけて続いたメキシコ革命下に起きた絵画運動です。メキシコ人としての誇りや過去の様々な抑圧の歴史、革命の意義などを字が読めない多くの国民に理解してもらおうとしたもので、メキシコのナショナリズムの復興に大きく貢献しました。
ディエゴ・リベラ、アルファロ・シケイロス、タマヨ、ホセ・クレメンテ・オロスコはメキシコ画壇の四大巨匠と呼ばれており、これらの人々の壁画作品はメキシコ国内にたくさん描かれています。
別の機会に報告しますが、グアダラハラの「オスピシオカバーニャス」(古い孤児院)はオロスコの壁画によって「世界文化遺産」に登録されています。
中央図書館に描かれたフアン・オゴルマンの壁画

陸上競技場の壁画

アメリカ大陸で2番目に古い大学だそうです。
どれくらいの広さかはわかりませんがとにかく広大なキャンパスに、メキシコオリンピックの会場にもなった陸上競技場などがあります。
この大学は、歴史的な多くの壁画が建物に描かれており、これらの壁画があることによって「世界文化遺産」に登録されています。
メキシコの壁画運動は、1910年代から40年頃にかけて続いたメキシコ革命下に起きた絵画運動です。メキシコ人としての誇りや過去の様々な抑圧の歴史、革命の意義などを字が読めない多くの国民に理解してもらおうとしたもので、メキシコのナショナリズムの復興に大きく貢献しました。
ディエゴ・リベラ、アルファロ・シケイロス、タマヨ、ホセ・クレメンテ・オロスコはメキシコ画壇の四大巨匠と呼ばれており、これらの人々の壁画作品はメキシコ国内にたくさん描かれています。
別の機会に報告しますが、グアダラハラの「オスピシオカバーニャス」(古い孤児院)はオロスコの壁画によって「世界文化遺産」に登録されています。
中央図書館に描かれたフアン・オゴルマンの壁画

陸上競技場の壁画

2010年10月14日
メキシコ旅行:マリアッチ
メキシコ旅行2日目の8月23日の夜はマリアッチが楽しめるメキシコ料理店で食事でした。
マリアッチとはメキシコのハリスコ州で誕生したメキシコを代表する演奏形式。
ヴァイオリンやギター、それに低音のギタロン、そしてトランペットが加わり、とっても陽気な歌と演奏を披露します。
結婚式やお祝いの場などで牧童達が演奏していたのが始まりのようで、服装も白い綿のマントにソンブレロというのがオリジナルのようですが、次第に着飾った服装に変化し、今ではテレビへ出演した有名な楽団が着た金属の飾りを付けた服装が主流になったようです。
 オリジナルに近い感じのマリアッチ人形
オリジナルに近い感じのマリアッチ人形
私たちはこの日の昼にもティオティワカン遺跡観光の途中で寄ったドライブインで、メキシコ料理とミニ・マリアッチ?(二人だけだったのでマリアッチとは呼ばないと思いますが)を楽しんでいました。

 お世辞にも上手ではなかったけどとても陽気なおじさん達でした。
お世辞にも上手ではなかったけどとても陽気なおじさん達でした。
メキシコシティのマリアッチライブハウスというべきこの店は、観光客だけでなく地元の人もたくさん来ているようで、夜10時過ぎというのに大にぎわいでした。
私たちはメキシコ料理も昨晩から3連続ということで、疲れと重なって「もういいです~~!!」という感じでしたが、マリアッチの演奏は結構楽しめました。とにかく陽気です。でも美空ひばりの「川の流れのように」を歌うのには驚きましたね。



マリアッチはこの後、マリアッチ発祥の地であるグアダラハラで、市の歓迎パーティーでも楽しみましたし、グアダラハラではマリアッチフェスティバルが開かれていたので、伝統的なマリアッチから現代版まで色々な演奏を楽しむことができました。


演奏レベルもピンからキリまであり、市の歓迎パーティーの楽団はさすがにピンでしたね。
こちらで歌ったのは長渕剛の「乾杯」・・・別にそこまでサービスしてくれなくてもいいのですがね。
マリアッチ以外にも今回の旅では色々なメキシコ音楽に出会いました。





とにかく音楽が好きな国民であることは間違いなさそうですね。
マリアッチとはメキシコのハリスコ州で誕生したメキシコを代表する演奏形式。
ヴァイオリンやギター、それに低音のギタロン、そしてトランペットが加わり、とっても陽気な歌と演奏を披露します。
結婚式やお祝いの場などで牧童達が演奏していたのが始まりのようで、服装も白い綿のマントにソンブレロというのがオリジナルのようですが、次第に着飾った服装に変化し、今ではテレビへ出演した有名な楽団が着た金属の飾りを付けた服装が主流になったようです。
 オリジナルに近い感じのマリアッチ人形
オリジナルに近い感じのマリアッチ人形 私たちはこの日の昼にもティオティワカン遺跡観光の途中で寄ったドライブインで、メキシコ料理とミニ・マリアッチ?(二人だけだったのでマリアッチとは呼ばないと思いますが)を楽しんでいました。

 お世辞にも上手ではなかったけどとても陽気なおじさん達でした。
お世辞にも上手ではなかったけどとても陽気なおじさん達でした。メキシコシティのマリアッチライブハウスというべきこの店は、観光客だけでなく地元の人もたくさん来ているようで、夜10時過ぎというのに大にぎわいでした。
私たちはメキシコ料理も昨晩から3連続ということで、疲れと重なって「もういいです~~!!」という感じでしたが、マリアッチの演奏は結構楽しめました。とにかく陽気です。でも美空ひばりの「川の流れのように」を歌うのには驚きましたね。



マリアッチはこの後、マリアッチ発祥の地であるグアダラハラで、市の歓迎パーティーでも楽しみましたし、グアダラハラではマリアッチフェスティバルが開かれていたので、伝統的なマリアッチから現代版まで色々な演奏を楽しむことができました。


演奏レベルもピンからキリまであり、市の歓迎パーティーの楽団はさすがにピンでしたね。
こちらで歌ったのは長渕剛の「乾杯」・・・別にそこまでサービスしてくれなくてもいいのですがね。
マリアッチ以外にも今回の旅では色々なメキシコ音楽に出会いました。





とにかく音楽が好きな国民であることは間違いなさそうですね。
2010年10月05日
ティオティワカン遺跡
8月23日は朝から「ティオティワカン遺跡」観光に向かいました。
今回の旅行のハイライトはなんと言ってもこの「ティオティワカン遺跡」です。
メキシコシティから50km北東に位置するこの遺跡は、紀元前2世紀から7世紀頃まで存在した巨大な宗教都市国家の遺跡です。
メキシコシティ周辺地域では、オルメカ文明→ティオティワカン文明→トルテカ文明→アステカ文明と変遷しています。
実際にこの宗教都市は、14世紀にアステカ人が発見して「ティオティワカン」つまり「神々の都市」という意味の名前を命名したのです。
主な建造物は
太陽のピラミッド (高さ65 m、底辺222 m×225 m)
月のピラミッド (高さ47 m、底辺140 m×150 m)
死者の大通り (南北に貫く都市のメインストリート 長さ4 km、幅45 m)
ケツァルパパロトルの宮殿(月のピラミッドに携わる神官の住居)
ケツァルコアトルの神殿(神々の彫像などで覆われた神殿)~残念ながら見れませんでした。 などです。
ピラミッドと言っても、エジプトのそれは王様のお墓ですが、こちらのピラミッドは宗教儀式のために造られたものだそうです。
それに、これらの巨大な建造物は幾層にもなっています。
つまり、ピラミッドの下にはその前の時代のピラミッドがあり、その下にもまたピラミッドがあるのです。同じように神殿の下にも神殿が幾重にも重なっています。
神様の世代交代??に合わせて数十年に一回新しい建造物が重なるように造られたそうです。
以上のようなうんちくはともかくとして、その壮大さ、建造物の美しさ、それらを取り巻く風景など筆舌につくし難いほど感動しました。おそらく1日眺めていても飽きることはないでしょう。ちょっと怖いかも知れませんが月夜の晩に来るとまた素晴らしい感動を得ることができるかもしれませんね。
それにしてもこの場所は標高2200mほどあるんですよ。
 月のピラミッド
月のピラミッド
 太陽のピラミッド
太陽のピラミッド
 死者の大通り
死者の大通り
 ケツァルパパロトルの宮殿
ケツァルパパロトルの宮殿
 月のピラミッドからの壮大な眺望
月のピラミッドからの壮大な眺望

 神殿内部の壁画
神殿内部の壁画
今回の旅行のハイライトはなんと言ってもこの「ティオティワカン遺跡」です。
メキシコシティから50km北東に位置するこの遺跡は、紀元前2世紀から7世紀頃まで存在した巨大な宗教都市国家の遺跡です。
メキシコシティ周辺地域では、オルメカ文明→ティオティワカン文明→トルテカ文明→アステカ文明と変遷しています。
実際にこの宗教都市は、14世紀にアステカ人が発見して「ティオティワカン」つまり「神々の都市」という意味の名前を命名したのです。
主な建造物は
太陽のピラミッド (高さ65 m、底辺222 m×225 m)
月のピラミッド (高さ47 m、底辺140 m×150 m)
死者の大通り (南北に貫く都市のメインストリート 長さ4 km、幅45 m)
ケツァルパパロトルの宮殿(月のピラミッドに携わる神官の住居)
ケツァルコアトルの神殿(神々の彫像などで覆われた神殿)~残念ながら見れませんでした。 などです。
ピラミッドと言っても、エジプトのそれは王様のお墓ですが、こちらのピラミッドは宗教儀式のために造られたものだそうです。
それに、これらの巨大な建造物は幾層にもなっています。
つまり、ピラミッドの下にはその前の時代のピラミッドがあり、その下にもまたピラミッドがあるのです。同じように神殿の下にも神殿が幾重にも重なっています。
神様の世代交代??に合わせて数十年に一回新しい建造物が重なるように造られたそうです。
以上のようなうんちくはともかくとして、その壮大さ、建造物の美しさ、それらを取り巻く風景など筆舌につくし難いほど感動しました。おそらく1日眺めていても飽きることはないでしょう。ちょっと怖いかも知れませんが月夜の晩に来るとまた素晴らしい感動を得ることができるかもしれませんね。

それにしてもこの場所は標高2200mほどあるんですよ。

 月のピラミッド
月のピラミッド 太陽のピラミッド
太陽のピラミッド  死者の大通り
死者の大通り ケツァルパパロトルの宮殿
ケツァルパパロトルの宮殿 月のピラミッドからの壮大な眺望
月のピラミッドからの壮大な眺望
 神殿内部の壁画
神殿内部の壁画2010年09月20日
メキシコ料理1軒目
丸1日近い旅の時差ぼけと疲労の中で早速地元、メキシコ京都クラブの橋本さんに連れて行っていただいたのがホテルから近いこのメキシコ料理店


あとで考えると最もメキシコらしいというかかなり上級者向けの店だったような気がします。
とにかくメキシコ料理と言えば「トルティージャ」
トウモロコシの生地を丸くのばして焼いたものです。
これに肉など色々なネタを挟み、サルサ(ソース)を塗って包むと有名な「タコス」



油で揚げれば「トスターダス」
辛いソースに浸せば「エンチターダス」
などと、日本のご飯が色々と姿・名前を変えるようなものです。
それにアボガドやサボテンなどの食材が印象的でした。
アボガドはサルサの材料etc
サボテンはスープの材料etc


ビールも色々な種類があります。
この日はとりあえず有名なコロナとボヘミアでした。
メキシコの人は、これらの料理をがんがん食べるそうですが、
私たちは疲れもあって「少食~~!!」
いきなりメキシコ料理の洗礼を受けた感じでしたね
メキシコ料理についてはもう一度まとめて報告しましょう。


あとで考えると最もメキシコらしいというかかなり上級者向けの店だったような気がします。
とにかくメキシコ料理と言えば「トルティージャ」
トウモロコシの生地を丸くのばして焼いたものです。
これに肉など色々なネタを挟み、サルサ(ソース)を塗って包むと有名な「タコス」



油で揚げれば「トスターダス」
辛いソースに浸せば「エンチターダス」
などと、日本のご飯が色々と姿・名前を変えるようなものです。
それにアボガドやサボテンなどの食材が印象的でした。
アボガドはサルサの材料etc
サボテンはスープの材料etc


ビールも色々な種類があります。
この日はとりあえず有名なコロナとボヘミアでした。
メキシコの人は、これらの料理をがんがん食べるそうですが、
私たちは疲れもあって「少食~~!!」
いきなりメキシコ料理の洗礼を受けた感じでしたね

メキシコ料理についてはもう一度まとめて報告しましょう。
タグ :メキシコ
2010年09月18日
メキシコシティ
メキシコシティ
8月22日の7時10分に福岡空港を出発、関西から来た訪問団一行と合流した私たちは、成田空港を11時30分に出発し、11時間40分後にアメリカのダラス・フォートワース空港に到着。メキシコの首都であるメキシコシティには8月22日の14時30分に到着しました。なんと21時間30分の旅でした。

ダラス・フォートワース空港
その広さに圧倒されます

メキシコシティorグアダラハラの空港
メキシコシティは、アステカ王国時代は「テノチティトラン」と呼ばれ、テスココ湖の湖上に築かれた壮麗な都市だったそうです。
1519年にスペイン人のエルナン・コルテスの征服によってことごとく破壊され、湖は埋め立てられて現在のスペイン風の都市が建設されました。
おかげで、メキシコシティはとても地盤が悪く、建物は毎年数センチづつ沈むそうです。
信じられません。でもこれは本当のことで、確かに街全体が「うねっている」のが良くわかります。数メートル地盤沈下した建物もたくさんあります。
また、スペイン人に財宝を渡してはならないと、アステカ人はすべての財宝を湖に沈めたそうですが、それを知らないスペイン人が湖を埋め立てたために、今でも膨大な財宝が湖底に眠っているそうです。
ヨーロッパからそのまま持ってきたようなメキシコシティの古い建物群はそれだけでもとても魅力的です。それもそのはず、メキシコシティの歴史地区は世界遺産に登録されています。でも、もし現代に「テノチティトラン」が残っていれば・・・これはもう超すごいでしょうね。






街中にヨーロッパ風の古い石造りの建物が見られます。
1968年に開かれたメキシコオリンピックや、1985年に発生したメキシコ大地震を経て、現在は2000~2200万人、世界第2位の人口を持つ中南米を代表する大都市に成長しています。
メキシコに行って来たというと友人から「暑かったでしょう」と言われます。
とんでもない! 標高2240mのメキシコシティは、夏でも最高気温25度程度、夜は15度程度まで下がり、湿度も低くてとても過ごしやすい街でした。
標高が高いため空気が薄いと聞いていましたが、それほど心配するほどではありません。
でも、知らない間に疲れがたまる感じはありましたね。
飛行機から見ると、とにかくどこまでも建物が広がっているのがわかります。
なだらかな丘陵に向かってレンガ造りの住宅地がすごい範囲で広がっています。
日本人の感覚では間違いなく丘陵地に高級住宅地が広がっているように見えます。
ところが実はこれが到着してからの案内ですべて「スラム街」ということがわかったときにはあっと驚きました。なんとこのスラム街は100万人を超えてるそうです。
福岡市の人口と一緒と思うとそのすごさがわかります。
ただ、東南アジア辺りの本当に貧しく不衛生なスラムとやはりちょっと違うような気もします。


日銭を稼いではレンガを買ってきて少しづつ家ができあがっていきます。
また、交通渋滞のすごさは言葉では言い表せません。
道路はとっても広くて少なくとも片側3車線はあるのに、都心部から郊外に向けて延々と渋滞が続いています。都心部に通勤する人は毎日何時間かけて通勤しているのでしょうか。
バスや鉄軌道も整備されているようですが、人口増加に追いつかないのでしょう。
私たちが行ったときはスモッグは聞いていたのとは違って全くありませんでしたが、季節によってはどうなのでしょうか。



本当に想像を絶する渋滞です。
私たちと一緒だった小学6年の女の子が夏休みの宿題の作文でメキシコの印象としてこの大渋滞を取り上げていたそうです。古代遺跡より渋滞ですか??
このバス専用レーンを走っている赤いバスは、日本では基幹バスと呼ばれています。
なんと3両連結バスがありました。
なんと、メキシコでは30分で車の運転免許証がもらえるそうです。
みんな免許証をもらってから、夜などに親や知り合いの車で運転の練習をするそうです。
ですから交通ルールは全く教えられません。「めちゃくちゃ」です。
それにガソリンも50~60円と安いので誰も車を離さない。
それでも何とかなっているのはさすが「中南米」のおおらかさなのでしょう。
日本人は絶対にまねできませんね。
それともう一つ印象的だったのは、人の多さです。
平日の昼というのに、街中どこでも「人・人・人」です。
どの街角でも太ったおじさんが椅子に座って、数人が取り囲んで話し込んでいます。
歩道は、色々なものを売っている人、通行人などであふれています。


若い人が多いのも特徴です。
なんとメキシコは20歳以下の人口が70%だそうです。
少子高齢化が進む日本からみればうらやましい限りです。
日本と比べればまだまだ貧しい国ですが、
「陽が昇る国」という印象を強く持ちました。
陽が沈みつつある日本とは正反対の活気を感じることができました。
2010年9月16日はメキシコ独立200周年だそうです。
ビバ・メヒコ!!
8月22日の7時10分に福岡空港を出発、関西から来た訪問団一行と合流した私たちは、成田空港を11時30分に出発し、11時間40分後にアメリカのダラス・フォートワース空港に到着。メキシコの首都であるメキシコシティには8月22日の14時30分に到着しました。なんと21時間30分の旅でした。

ダラス・フォートワース空港
その広さに圧倒されます

メキシコシティorグアダラハラの空港
メキシコシティは、アステカ王国時代は「テノチティトラン」と呼ばれ、テスココ湖の湖上に築かれた壮麗な都市だったそうです。
1519年にスペイン人のエルナン・コルテスの征服によってことごとく破壊され、湖は埋め立てられて現在のスペイン風の都市が建設されました。
おかげで、メキシコシティはとても地盤が悪く、建物は毎年数センチづつ沈むそうです。
信じられません。でもこれは本当のことで、確かに街全体が「うねっている」のが良くわかります。数メートル地盤沈下した建物もたくさんあります。
また、スペイン人に財宝を渡してはならないと、アステカ人はすべての財宝を湖に沈めたそうですが、それを知らないスペイン人が湖を埋め立てたために、今でも膨大な財宝が湖底に眠っているそうです。
ヨーロッパからそのまま持ってきたようなメキシコシティの古い建物群はそれだけでもとても魅力的です。それもそのはず、メキシコシティの歴史地区は世界遺産に登録されています。でも、もし現代に「テノチティトラン」が残っていれば・・・これはもう超すごいでしょうね。


街中にヨーロッパ風の古い石造りの建物が見られます。
1968年に開かれたメキシコオリンピックや、1985年に発生したメキシコ大地震を経て、現在は2000~2200万人、世界第2位の人口を持つ中南米を代表する大都市に成長しています。
メキシコに行って来たというと友人から「暑かったでしょう」と言われます。
とんでもない! 標高2240mのメキシコシティは、夏でも最高気温25度程度、夜は15度程度まで下がり、湿度も低くてとても過ごしやすい街でした。
標高が高いため空気が薄いと聞いていましたが、それほど心配するほどではありません。
でも、知らない間に疲れがたまる感じはありましたね。
飛行機から見ると、とにかくどこまでも建物が広がっているのがわかります。
なだらかな丘陵に向かってレンガ造りの住宅地がすごい範囲で広がっています。
日本人の感覚では間違いなく丘陵地に高級住宅地が広がっているように見えます。
ところが実はこれが到着してからの案内ですべて「スラム街」ということがわかったときにはあっと驚きました。なんとこのスラム街は100万人を超えてるそうです。
福岡市の人口と一緒と思うとそのすごさがわかります。
ただ、東南アジア辺りの本当に貧しく不衛生なスラムとやはりちょっと違うような気もします。
日銭を稼いではレンガを買ってきて少しづつ家ができあがっていきます。
また、交通渋滞のすごさは言葉では言い表せません。
道路はとっても広くて少なくとも片側3車線はあるのに、都心部から郊外に向けて延々と渋滞が続いています。都心部に通勤する人は毎日何時間かけて通勤しているのでしょうか。
バスや鉄軌道も整備されているようですが、人口増加に追いつかないのでしょう。
私たちが行ったときはスモッグは聞いていたのとは違って全くありませんでしたが、季節によってはどうなのでしょうか。

本当に想像を絶する渋滞です。
私たちと一緒だった小学6年の女の子が夏休みの宿題の作文でメキシコの印象としてこの大渋滞を取り上げていたそうです。古代遺跡より渋滞ですか??
このバス専用レーンを走っている赤いバスは、日本では基幹バスと呼ばれています。
なんと3両連結バスがありました。
なんと、メキシコでは30分で車の運転免許証がもらえるそうです。
みんな免許証をもらってから、夜などに親や知り合いの車で運転の練習をするそうです。
ですから交通ルールは全く教えられません。「めちゃくちゃ」です。
それにガソリンも50~60円と安いので誰も車を離さない。
それでも何とかなっているのはさすが「中南米」のおおらかさなのでしょう。
日本人は絶対にまねできませんね。
それともう一つ印象的だったのは、人の多さです。
平日の昼というのに、街中どこでも「人・人・人」です。
どの街角でも太ったおじさんが椅子に座って、数人が取り囲んで話し込んでいます。
歩道は、色々なものを売っている人、通行人などであふれています。
若い人が多いのも特徴です。
なんとメキシコは20歳以下の人口が70%だそうです。
少子高齢化が進む日本からみればうらやましい限りです。
日本と比べればまだまだ貧しい国ですが、
「陽が昇る国」という印象を強く持ちました。
陽が沈みつつある日本とは正反対の活気を感じることができました。
2010年9月16日はメキシコ独立200周年だそうです。
ビバ・メヒコ!!

タグ :メキシコ
2010年09月16日
メキシコ行って来ました
日墨交流400周年、京都・グアダラハラ姉妹都市盟約30周年記念親善団に参加してメキシコまで行って来ました。
海外にはほとんど行ったことがないというか、夫婦で行くのは今回が初めての私たちが、まさかメキシコに行くことになるとは考えたこともありませんでした。
そのきっかけを作ってくれたのは私たちの息子です。
京都市とメキシコのグアダラハラ市が姉妹都市になって30年目の年、30周年記念親善団がメキシコを訪問することになり、その記念事業の一つとして行われるコンサートで息子がピアノを演奏することになったからです。
だからといって、親まで行かなくてもと思うのですが、親善団の関係の旅行会社からお誘いがあったので、こんなチャンスでもないとメキシコはさすがに行くことないだろうと思い思い切って参加しました。
以下が公式行事日程です。

メキシコシティ
8月23日
・親善相撲公演
・日墨交流400周年記念公演
8月24日
・日墨協会主催 フェアウェル昼食会~宮下和夫ピアノ親善公演
グアダラハラ
8月25日
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念調印式
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念親善公演
§コンサート~ピアノ:真隅政大、オーケストラ:ハリスコ州立交響楽団
・グアダラハラ市主催歓迎パーティー
8月26日
・親善相撲公演
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念親善公演
§女人舞楽、宮下バレエ団、京小町踊り子隊
・京都市主催答礼パーティー
この一大イベントは「京都メキシコ文化協会」が主催したものです。
京都市の市長や議長、グアダラハラ市の市長などが参加しての公式行事もありました。
それはさておいても、普通の旅行では体験できない貴重な旅でした。
その様な公式行事の合間を縫って、オプションのツアーも組まれていました。
私たちの旅行日程は次のとおりバラエティーに富んでいました。
8月22日(日)7:10出発
・福岡~成田~ダラス~メキシコシティ
・21時間35分の旅(飛行時間合計15時間)
・14:45メキシコシティ到着
・ホテル:ガレリア プラザ メキシコシティ
・夕食はホテル近くの小さなメキシコ料理店へ
8月23日(月)
・ティオティーワカン遺跡観光
・マリアッチとメキシコ料理
8月24日(火)
・メキシコシティ市内ドライブ観光
・日墨協会主催 フェアウェル昼食会~宮下和夫ピアノ親善公演
・グアダラハラへ移動(空路約1時間半)
・ホテル:ホテル デ メンドーサ
8月25日(水)
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念調印式
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念親善公演
§コンサート~ピアノ:真隅政大、オーケストラ:ハリスコ州立交響楽団
・グアダラハラ市主催歓迎パーティー
8月26日(木)
・親善相撲公演
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念親善公演
§女人舞楽、宮下バレエ団、京小町踊り子隊
・京都市主催答礼パーティー
8月27日(金)
・テキーラ村観光
・親善団によるさよなら夕食会
8月28日(土)
・グアダラハラ出発 8:15 ダラス経由
8月27日(日)
・成田着 15:25
・福岡着 21:55(30分遅れ)
それでは、これから何回かに分けてメキシコシリーズを始めたいと思います。乞うご期待です。

海外にはほとんど行ったことがないというか、夫婦で行くのは今回が初めての私たちが、まさかメキシコに行くことになるとは考えたこともありませんでした。

そのきっかけを作ってくれたのは私たちの息子です。
京都市とメキシコのグアダラハラ市が姉妹都市になって30年目の年、30周年記念親善団がメキシコを訪問することになり、その記念事業の一つとして行われるコンサートで息子がピアノを演奏することになったからです。
だからといって、親まで行かなくてもと思うのですが、親善団の関係の旅行会社からお誘いがあったので、こんなチャンスでもないとメキシコはさすがに行くことないだろうと思い思い切って参加しました。
以下が公式行事日程です。

メキシコシティ
8月23日
・親善相撲公演
・日墨交流400周年記念公演
8月24日
・日墨協会主催 フェアウェル昼食会~宮下和夫ピアノ親善公演
グアダラハラ
8月25日
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念調印式
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念親善公演
§コンサート~ピアノ:真隅政大、オーケストラ:ハリスコ州立交響楽団
・グアダラハラ市主催歓迎パーティー
8月26日
・親善相撲公演
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念親善公演
§女人舞楽、宮下バレエ団、京小町踊り子隊
・京都市主催答礼パーティー
この一大イベントは「京都メキシコ文化協会」が主催したものです。
京都市の市長や議長、グアダラハラ市の市長などが参加しての公式行事もありました。
それはさておいても、普通の旅行では体験できない貴重な旅でした。
その様な公式行事の合間を縫って、オプションのツアーも組まれていました。
私たちの旅行日程は次のとおりバラエティーに富んでいました。
8月22日(日)7:10出発
・福岡~成田~ダラス~メキシコシティ
・21時間35分の旅(飛行時間合計15時間)
・14:45メキシコシティ到着
・ホテル:ガレリア プラザ メキシコシティ
・夕食はホテル近くの小さなメキシコ料理店へ
8月23日(月)
・ティオティーワカン遺跡観光
・マリアッチとメキシコ料理
8月24日(火)
・メキシコシティ市内ドライブ観光
・日墨協会主催 フェアウェル昼食会~宮下和夫ピアノ親善公演
・グアダラハラへ移動(空路約1時間半)
・ホテル:ホテル デ メンドーサ
8月25日(水)
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念調印式
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念親善公演
§コンサート~ピアノ:真隅政大、オーケストラ:ハリスコ州立交響楽団
・グアダラハラ市主催歓迎パーティー
8月26日(木)
・親善相撲公演
・京都市グアダラハラ市姉妹盟約30周年記念親善公演
§女人舞楽、宮下バレエ団、京小町踊り子隊
・京都市主催答礼パーティー
8月27日(金)
・テキーラ村観光
・親善団によるさよなら夕食会
8月28日(土)
・グアダラハラ出発 8:15 ダラス経由
8月27日(日)
・成田着 15:25
・福岡着 21:55(30分遅れ)
それでは、これから何回かに分けてメキシコシリーズを始めたいと思います。乞うご期待です。

タグ :メキシコ
2010年08月13日
貴船神社
 ついこの間、用事ができて京都に言ったついでに、京都北部の貴船神社にお参りしてきました。
ついこの間、用事ができて京都に言ったついでに、京都北部の貴船神社にお参りしてきました。京福電鉄の出町柳駅から叡山電車鞍馬線の電車に乗って約30分弱、終点鞍馬駅の一つ手前の貴船口駅で下車して、小さなバスに乗り換えると貴船街道を10分足らずで貴船神社下のバス停に到着します。
それほど標高の高い場所ではないので涼しいと言うほどではないのですが、それでも貴船川のせせらぎ沿いの道を歩くのは気持ちの良いものです。

貴船神社は1600年も前に創建されたとも言われる水を司る神社です。
今の大阪湾に黄色い船に乗った女の神様が現れ「われは玉依姫なりこの船の留まるところに社殿を建ててそこの神様を大事にお祀りすれば国土を潤し庶民に福運を与えん」とのお告げがあり、淀川、鴨川をさかのぼって水源の地に船を留め社殿を建てたのが奥宮と伝えられています。
黄色い船だから「黄船=貴船」?絶対に怪しいですが。
水の神様なのに、なぜか縁結びの神様としても若いカップルに人気の神社です。
なぜ?・・・・昔、 和泉式部さんがお詣りし夫と復縁したそうです。

その他、心願成就、航海安全、火防せの神様として信仰されています。
今の時期は、川床がとても有名で、休日は予約しないと受け入れてもらえません。
賀茂川の川床は、「ほんとうにくっそ暑そう」であまり経験したいとは思いませんが、貴船の川床はなかなか涼しそうです。
まずは、貴船神社の本宮をお参りしました。


そんな川床を後目に、500mほど上流の奥宮まで散歩してきました。
この道をずっと行くと、木の根道、大原御幸で有名な鞍馬街道へとつながります。



昔は2~3軒の茶店しかなかったように記憶していますが、いまは20軒くらいの店が軒を連ねています。でも喫茶店が1軒しかないのは意外でした。きっと冬など誰も来ないのでしょうね。




学生時代以来、35年ぶりの訪問
今日は、嫁と娘と3人ですが、あのときは・・・・・・??

タグ :京都
2010年05月23日
ヨーロッパ各停列車で行くハイドンの旅
福岡市民オーケストラの旧友が本を出しました。
幻冬舎ルネッサンス新書「ヨーロッパ各停列車で行くハイドンの旅」という本です。
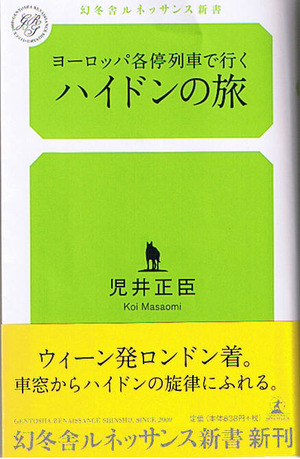
著者は、児井正臣(こいまさおみ)氏
彼は、福岡市民オーケストラの記録を確認すると、
1981年6月7日の「ラブリーコンサート」から、
1981年11月15日の第10回定期演奏会を経て、
1984年11月3日の第16回定期演奏会まで、
約4年間在籍して、オーボエを吹いていました。
30年近く前のことなんです。
驚きますね~~・・・いやいや単に私が年取っただけ?
2004年に日本アイ・ビー・エムを退職されて、
趣味をベースのとても豊かな人生を送られているようです。
「ヨーロッパ各停列車で行くハイドンの旅」とうい本は、
鉄道ファン・・・おそらく乗り鉄??・・・である豊富な知識と、
オーケストラを体験していたハイドンファンとしての好奇心が融合した、
興味深い紀行本だと思います。
本人も書いておられるように、
鉄道のうんちくは素人向けにごく控えめに書かれており、
とっても読みやすい旅の本という感じにまとめられています。
この本は2005年から2008年まで、
4回にわたってそれぞれ2~3週間ずつ渡欧し、
ウィーンからイギリスまでハイドンが辿ったであろう土地を、
列車で、それも主に各停列車に乗車しながら旅して書かれたものです。
ハイドンは晩年、1791年から1792年と1794年から1795年の2度イギリスを訪問しています。
ロンドン交響曲と呼ばれる12曲の交響曲を発表していますが、交響曲第100番「軍隊」101番「時計」104番「ロンドン」など編成が大きく、現代最も頻繁に演奏されるハイドンの交響曲はこの時に作曲されたものです。
第一章は「ウィーンとその周辺」
第二章は「オーストリア国内を西へ」
第三章は「ドイツ横断」
第四章は「ルクセンブルク、ベルギーからフランス北部へ」
第五章は「イギリス上陸からロンドンへ」
第六章は「その後のハイドン」
表題を見ただけでも「行ってみたいな~~~!!」
という気分になります。
本は、ハイドンの生家や、成人するまでに活動した場所、ハイドンが30年間仕事をしたエステルハージー侯爵家の城、モーツァルトやベートーベンが活躍したウィーンのザルツブルグやドイツのボンなど音楽ゆかりの土地などを案内しながら、イギリスのロンドンやオクスフォードなど、ハイドンが活躍したイギリスの都市を巡ります。
本を読むと、よくもまあこれだけ行き当たりばったり??色々な各駅停車の列車やバスを乗りまくったなと本当に感心してしまいます。
日本でも鉄道を乗りまくっておられる著者の鉄道に対する「嗅覚」というようなものが、こっちの方が面白いよ~~~!!と誘うのでしょうか。
それと、彼のお嬢さんは今、スイスのルツェルン交響楽団とルツェルン・フェスティバル・ストリングという室内アンサンブルで第2ヴァイオリンを弾いておられるそうです。
これもまたこの壮大な旅の支えと動機になったようです。
ハイドンの時代、クラシック音楽の中心地だったヨーロッパの車窓の風景と、
日本の鉄道と比較しながらちょっぴり鉄道のうんちくがでてきて、
ついつい「へ~~!!」と言って旅の気分を味わわせてくれる、
クラシックファンならずとも、また鉄道ファンならずとも
とても楽しい本ですよ。
児井さ~~ん。
すてきな旅をありがとうございました。
幻冬舎ルネッサンス新書「ヨーロッパ各停列車で行くハイドンの旅」という本です。
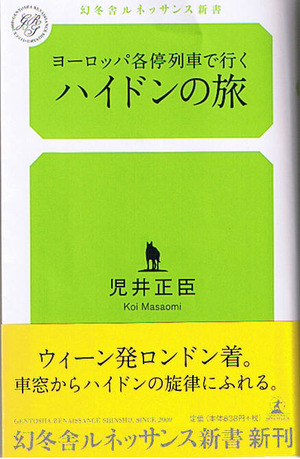
著者は、児井正臣(こいまさおみ)氏
彼は、福岡市民オーケストラの記録を確認すると、
1981年6月7日の「ラブリーコンサート」から、
1981年11月15日の第10回定期演奏会を経て、
1984年11月3日の第16回定期演奏会まで、
約4年間在籍して、オーボエを吹いていました。
30年近く前のことなんです。
驚きますね~~・・・いやいや単に私が年取っただけ?
2004年に日本アイ・ビー・エムを退職されて、
趣味をベースのとても豊かな人生を送られているようです。
「ヨーロッパ各停列車で行くハイドンの旅」とうい本は、
鉄道ファン・・・おそらく乗り鉄??・・・である豊富な知識と、
オーケストラを体験していたハイドンファンとしての好奇心が融合した、
興味深い紀行本だと思います。
本人も書いておられるように、
鉄道のうんちくは素人向けにごく控えめに書かれており、
とっても読みやすい旅の本という感じにまとめられています。
この本は2005年から2008年まで、
4回にわたってそれぞれ2~3週間ずつ渡欧し、
ウィーンからイギリスまでハイドンが辿ったであろう土地を、
列車で、それも主に各停列車に乗車しながら旅して書かれたものです。
ハイドンは晩年、1791年から1792年と1794年から1795年の2度イギリスを訪問しています。
ロンドン交響曲と呼ばれる12曲の交響曲を発表していますが、交響曲第100番「軍隊」101番「時計」104番「ロンドン」など編成が大きく、現代最も頻繁に演奏されるハイドンの交響曲はこの時に作曲されたものです。
第一章は「ウィーンとその周辺」
第二章は「オーストリア国内を西へ」
第三章は「ドイツ横断」
第四章は「ルクセンブルク、ベルギーからフランス北部へ」
第五章は「イギリス上陸からロンドンへ」
第六章は「その後のハイドン」
表題を見ただけでも「行ってみたいな~~~!!」

という気分になります。
本は、ハイドンの生家や、成人するまでに活動した場所、ハイドンが30年間仕事をしたエステルハージー侯爵家の城、モーツァルトやベートーベンが活躍したウィーンのザルツブルグやドイツのボンなど音楽ゆかりの土地などを案内しながら、イギリスのロンドンやオクスフォードなど、ハイドンが活躍したイギリスの都市を巡ります。
本を読むと、よくもまあこれだけ行き当たりばったり??色々な各駅停車の列車やバスを乗りまくったなと本当に感心してしまいます。

日本でも鉄道を乗りまくっておられる著者の鉄道に対する「嗅覚」というようなものが、こっちの方が面白いよ~~~!!と誘うのでしょうか。
それと、彼のお嬢さんは今、スイスのルツェルン交響楽団とルツェルン・フェスティバル・ストリングという室内アンサンブルで第2ヴァイオリンを弾いておられるそうです。
これもまたこの壮大な旅の支えと動機になったようです。
ハイドンの時代、クラシック音楽の中心地だったヨーロッパの車窓の風景と、
日本の鉄道と比較しながらちょっぴり鉄道のうんちくがでてきて、
ついつい「へ~~!!」と言って旅の気分を味わわせてくれる、
クラシックファンならずとも、また鉄道ファンならずとも
とても楽しい本ですよ。
児井さ~~ん。
すてきな旅をありがとうございました。

2010年03月21日
金閣寺
先日の上洛で久しぶりというか30数年ぶりに金閣寺に行ってきました。
陽の光に照らされて、とってもとってもビューティフル・・・でした。


金閣寺の派手さはあまり好きではないので訪問は今回でたったの2回目です。
大好きな銀閣寺にはおそらく十数回、いやそれ以上拝観しています。
でも、今回見た金閣寺は素晴らしいものでした。
派手さもここまで来れば文句のつけようがありませんね。
金閣寺は通称で、本当の名前は鹿苑寺(ろくおんじ)。
臨済宗相国寺派の寺院。
1397年に足利義満が建立し「北山殿」と呼ばれていました。
1950年に修行僧の放火によって全焼してしまったことはあまりにも有名。
現在の金閣は1955年に再現されたものだが金箔の質が悪く30数年前に見たときは黒ずんでたことを覚えています。
今回見た金閣寺は「昭和大修復」で1987年に生まれ変わったものです。
ちなみに、銀閣寺は慈照寺(じしょうじ) 。
同じく臨済宗相国寺派の寺院です。
1490年に足利義政が建立し「東山殿」と呼ばれていました。
こちらは正真正銘本物です。


陽の光に照らされて、とってもとってもビューティフル・・・でした。


金閣寺の派手さはあまり好きではないので訪問は今回でたったの2回目です。
大好きな銀閣寺にはおそらく十数回、いやそれ以上拝観しています。
でも、今回見た金閣寺は素晴らしいものでした。
派手さもここまで来れば文句のつけようがありませんね。

金閣寺は通称で、本当の名前は鹿苑寺(ろくおんじ)。
臨済宗相国寺派の寺院。
1397年に足利義満が建立し「北山殿」と呼ばれていました。
1950年に修行僧の放火によって全焼してしまったことはあまりにも有名。
現在の金閣は1955年に再現されたものだが金箔の質が悪く30数年前に見たときは黒ずんでたことを覚えています。
今回見た金閣寺は「昭和大修復」で1987年に生まれ変わったものです。
ちなみに、銀閣寺は慈照寺(じしょうじ) 。
同じく臨済宗相国寺派の寺院です。
1490年に足利義政が建立し「東山殿」と呼ばれていました。
こちらは正真正銘本物です。




